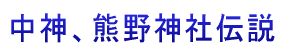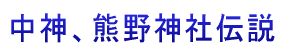| 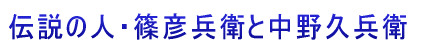
江戸時代、中神村から和歌山県の熊野三大社に数人が旅立った。
旅の長(おさ)を勤めるもの、篠彦兵衛といった。
おそらく彦兵衛は名主代か組頭であったろう。
彦兵衛一行は、伊勢神宮に参拝し、それから、
熊野総本山、三大社へ向かった。
熊野速玉大社・熊野本宮大社・熊野那智大社それぞれで、
三神のお札を拝領され、これを中神村に持ち帰る。
この旅は早く見積もったとしても、40日は掛かったであろう。
中神村に神仏の信仰深き人がいた。
名は中野久兵衛、8代目の中野久次郎当主の嫡男であった。
中野家は6代目で縞、織物などの仲買商で財を築いた。
7代目久次郎が初めて中野家として、名主になった。文政12年(1829年)
中神の獅子舞は、この前後ぐらいから、存在していたようだが
それ以前のことは定かでない。
嘉永4年(1851年)当時の熊野神社周辺は山林茂る森だった。
熊野大権現、御堂周辺は境内とは言い難い状況であったであろう、
したがって村の衆が集まり、獅子舞奉納など可能な広さがあったかは推測できない。
しかしながら現在、中神坂南にある日枝神社で獅子舞が、
演舞されていたとは伝承により高い確率で推定できる。
時代は幕末動乱に差し掛かっていた。(1853年,黒船来船)
1852年の初旬、中野久兵衛は熊野神社を再建すべく、誠心誠意、
尽力をそそぐのであった。一言で解釈すれば、寄進である。
鬱蒼(うっそう)と茂る森を切り開き、段丘に石垣を積む。
地所を平にして、神社境内を創設する。
三神のお札は社殿奧の御堂に安置され。
これをもって、熊野神社となった。嘉永5年(1852)。
由々しく存在する御堂の中に、拝領されたお札が安置されている。
しかしそれを、見た者は誰もいない。
それは絶対に見ては行けないという言い伝えがある。
熊野神社は延文5年(1360)の創建と伝えられています。
嘉永5年(1852)の再建。
歴史上では8代目、中野久次郎の寄進となる。
しかし伝説として、若き久兵衛の名がここに残る。
久兵衛はその名を残すが如く、9代目久兵衛と襲名した。
(昔語り・川島昭次 昭島郷土史・白川宗昭著書・参考)
|